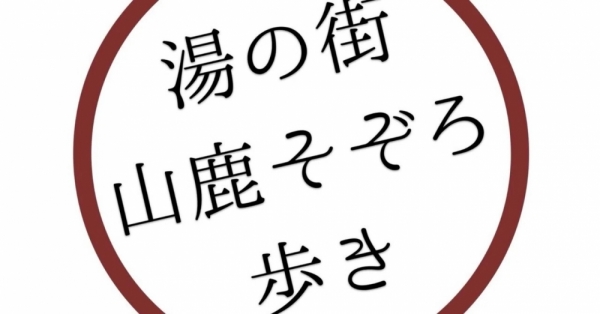
本日、Kindleペーパーバック版第5弾として『湯の街 山鹿そぞろ歩き』の出版登録が完了した。
A5判・112ページ程度の軽装本である。今回は写真を多用しているため、熊本県北部に位置する山鹿市の魅力を存分に伝えたいところだが、カラー印刷ができない点はやや残念である。
それでも、人口約5万人の小さな基礎自治体ながら、自然に恵まれ、食材も多種多様に揃う豊かな地域である。もちろん、水が清らかで潤沢なため、上質な米どころとしても名高い。
本日深夜にはKindleのレビューも完了する見込みで、まもなく購入可能になるだろう。さらに、先日販売を開始した『人間学厳選録|人の道』『痛い時代|ITAI深掘り』『西田親生流 Branding 洋菓子匠 維新之蔵|禁断の十字パイ』の3巻も手元に届き、実にご機嫌な一日となった。
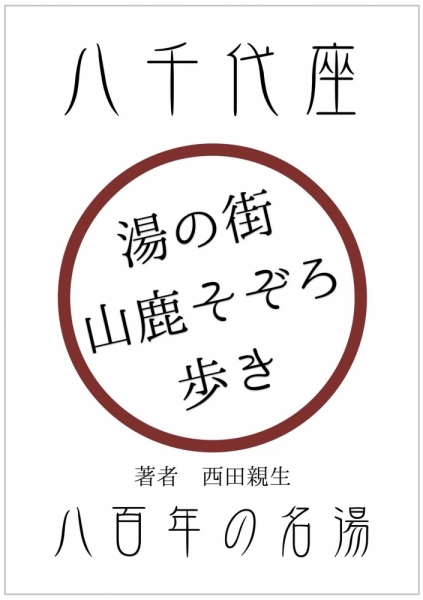
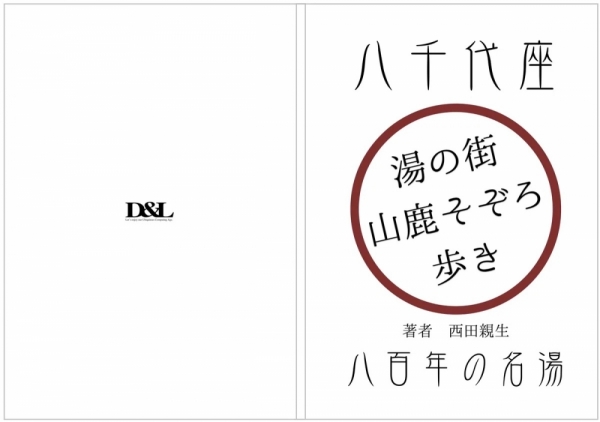
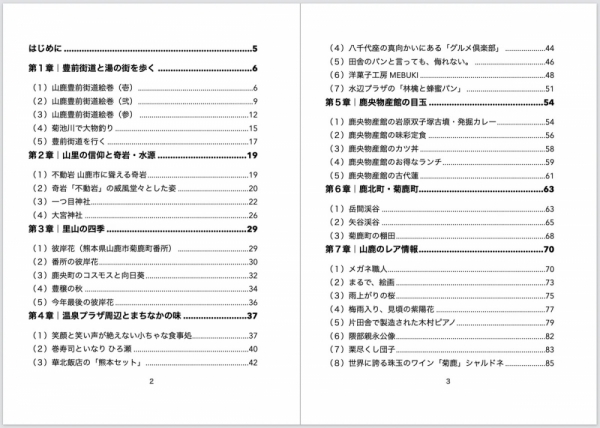
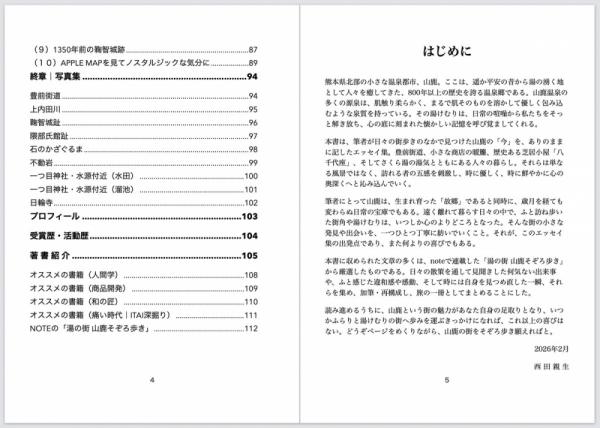
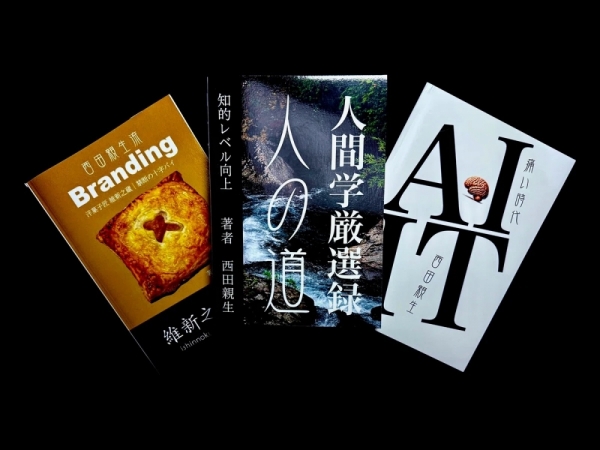
▼人間学厳選録|人の道
https://amzn.to/4c7F9GN
▼痛い時代|ITAI深掘り
https://amzn.to/4s7lmvN
▼西田親生流ブランディング|禁断の十字パイ
https://amzn.to/3Oxc4ea
▼脇宮盛久の世界|和の匠
https://amzn.to/4c7jvT4
----------
◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)
https://www.dandl.co.jp/
文責:西田親生

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)

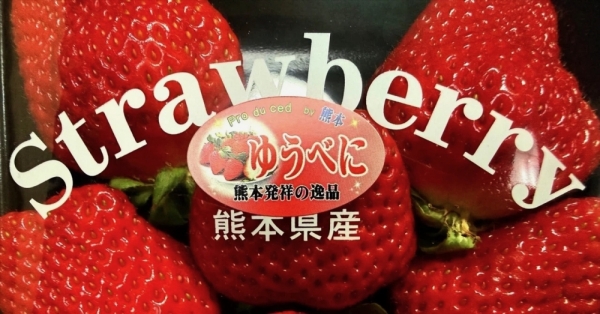

















Comments