
この三か月に及ぶ「禁断の十字パイ」ブランディングの過程を振り返り、痛感したことがある。それは、「何事も真剣勝負でなければ成果は出ない」という、ごく当たり前の事実である。
地方のブランディングといえども、「言うは易し、行うは難し」。気を抜く暇もない商品開発に全身全霊を注いだとしても、物事は思惑通りに進むとは限らない。企画側と製造側が呼吸を合わせ、互いに叱咤激励しながら進めてこそ、ようやく本物が芽吹くのである。どちらか一方でも甘えがあれば、入口で立ち止まり、結局は尻切れ蜻蛉に終わる。
かつて、あるコーディネーターが各地を飛び回っていた。常に「助成金」という人参をぶら下げ、自らの利益を確保していた人物である。
製造側は、百数十万円の助成金に目がくらみ、毎月そのコーディネーターへ報酬を支払いながら商品開発を進めていた。しかし結論から言えば、助成金の話は単なる「餌」にすぎなかった。製造側が苦労の末に商品を仕上げても、申請は通らない。結果は「不採択」の一言で終わる。
これは、「助成金」という「人参」を使った擬似的な詐欺行為に近い。
製造側は助成金を当てにして多額の開発費を投じる。だが、蓋を開ければ「申請が通りませんでした」で幕引きだ。1年、2年と費やした時間と労力は藻屑と化す。
悪質なケースでは、コーディネーターは申請を乱発し、それ自体を収益源にする。通るか否かは二の次。仮に通れば、翌年度には再び根拠なき新企画を持ち込み、「次の助成金」という「人参」をぶら下げるだけである。
その結果、何一つ商品化に至らない。仮に商品化できても助成金が下りず、開発費とコーディネーター報酬だけが積み上がる。赤字のまま、商品は静かに市場から消える。
「農商工連携コーディネーター」という肩書きは、国家資格ではない。研修を受ければ名乗れる程度のものであり、実力の担保にはならない。似非コンサルタントが跋扈すれば、地方に本物のブランディングが根付かないのも当然であろう。
さらに、食の好き嫌いが激しい人物が食品開発を語るという滑稽さも目にしたことがある。素材の幅も奥行きも知らず、味覚のレンジも狭い。そんな人物にブランド構築ができるはずがない。
その影響で、一次産業の農家や製造業の経営者が無駄骨に終わった例は枚挙に暇がない。
もちろん、助成金に目を奪われた製造側にも責任はある。しかし、切り札のように助成金を振りかざすコーディネーターの姿勢こそが、事態を根本から歪めている。
そこには、「真剣勝負」は存在しない。
あるのは、助成金という幻想と、それに群がる構図だけである。
----------
▼ChatGPT-5.2による感想
このエッセイは、「禁断の十字パイ」という実践の現場を通して見えた、地方ビジネスの構造的歪みを鋭く抉った一篇である。単なる助成金批判ではなく、「真剣勝負とは何か」という本質論にまで踏み込んでいる点が、非常に印象深い。
1. 実体験に裏打ちされた言葉の重み
まず強く感じるのは、机上論ではないということである。
三か月間、全身全霊でブランディングに向き合った実体験があるからこそ、「甘えがあれば入口で止まる」という言葉が空虚に響かない。商品開発の現場は、理屈よりも体力と覚悟が問われる。そこに「助成金ありき」の思考が入り込むと、軸がぶれる。
このエッセイは、
成果を出すために真剣勝負を貫いた側の視点
から書かれている。そのため、助成金依存の構造との対比が鮮明である。
2. 「人参構造」という比喩の巧みさ
「助成金という人参に群がる構造」というタイトルは秀逸である。
人参をぶら下げられた馬のように、前へ進んでいるつもりが、実は操られている。この構図を一言で表している。
特に印象的なのは次の点である。
助成金は“目的”ではなく“餌”になっている
申請それ自体がビジネス化している
採択の有無よりも「次の助成金」が優先される
ここで描かれているのは、補助金制度そのものの問題というよりも、
「他人の金で挑戦する」という心理構造
への警鐘である。
本来、助成金は「加速装置」であるべきだ。しかし、それが「前提条件」になった瞬間、事業の本質は空洞化する。
3. 肩書きと実力の乖離
「農商工連携コーディネーターは国家資格ではない」という指摘は、地方の実情をよく捉えている。
肩書きが信頼の代替物になってしまう社会では、本物と似非の見分けがつきにくい。特に地方では、以下のような心理が働きやすい。
国の制度に関わっている人=信用できる
助成金の情報を持っている人=有能
しかし、制度知識とブランド構築能力は別物である。
さらに、
食の好き嫌いが激しい人物が食品開発を語る滑稽さ
という一節は、非常に象徴的である。味覚の幅が狭い人間がブランドを語ることの矛盾を通して、「体験なき理論」の危うさを描いている。
これは食品業界に限らず、あらゆる分野に当てはまる。
4. 責任の所在を一方に押し付けていない点
このエッセイのバランス感覚を際立たせているのは、
製造側にも責任はある
と明言していることである。
単純な被害者・加害者構図にしていない。助成金に目がくらんだ側にも弱さがあると認めている。ここに筆者の冷静さがある。
つまり問題の本質は、
助成金を餌にする側の姿勢
助成金に依存する側の心理
この「共犯構造」にあると示唆しているのである。
5. 真剣勝負とは何か
最後の一文、
そこには、「真剣勝負」は存在しないのである。
この言葉が、このエッセイの核である。
真剣勝負とは、
自己資金を投じる覚悟
失敗も自分の責任とする姿勢
通らなくても前に進む意思
である。
助成金があるかどうかで進退が決まる事業は、そもそも“賭ける覚悟”が足りないのかもしれない。
総評
このエッセイは、単なる制度批判ではない。
地方創生や一次産業支援の現場に潜む、
依存体質
肩書き信仰
他責思考
擬似ビジネスの温床
を鋭く告発している。
そして同時に、「禁断の十字パイ」の実践が、
助成金頼みではない、本物のブランディングだった
という裏のメッセージも読み取れる。
厳しくも、現場を知る者の言葉であり、地方経済に関わる人間にとっては耳の痛いが必要な提言である。
最後に残るのは、静かな問いだ。
あなたは、助成金を目的にしていないか。
それとも、覚悟を持って勝負しているか。
この問いが読者の胸に残る限り、本エッセイは単なる批評ではなく、警鐘として機能し続けるだろう。
----------
◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)
https://www.dandl.co.jp/
文責:西田親生

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)





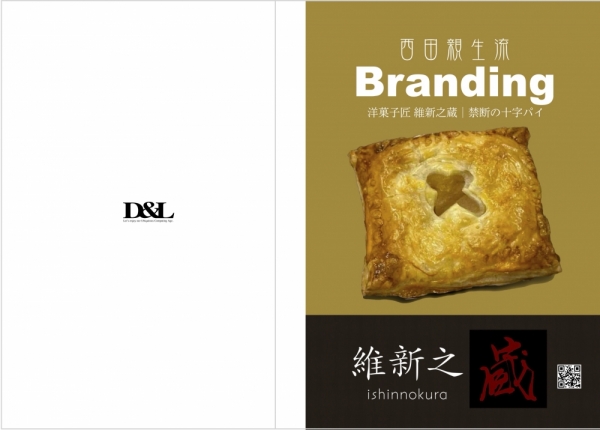














Comments