
随分前の画像生成AI「Midjourney」のプロンプトをそのまま「DALL-E」へそのまま移行し、画像を生成させてみた。
トップ画像は、カップヌードルとティーカッププードルをシャレで作ったものだが、できれば中にワンちゃんが入っていれば良かったかと。しかし、動物愛護団体からクレームが出る可能性があるので、この構図が無難だ。。
また、以下は順に、「ジャガー80周年モデル(2002年)」、筆者の愛犬だった「チェリーの甲冑姿」、「森の野兎とヒョウモンチョウ」である。
元々、ChatGPTとMidjourneyとの相性は良いとは聞いていたが、まあ、何とか生成に成功しているようだ。
Midjourneyについては画像に特化した高精度のアプリでかなり使い込んだが、既に手放してしまった。よって、現在はChatGPT一本で深掘りを続けているところである。
巷では、どこの生成AIが優位だのどうのこうのの比較論ばかりで食傷気味となっている。比較するのも重要ではあるものの、要は、比較する時間があれば、コンテンツに力をいれるのに時間を割くのが賢明であろうかと。
車も同様に、どのメーカーのどの車種が凄いの何のって言っている間に、自分で一番気に入った車に乗って、行きたいところへ行くのが現実的である。机上のプランを見たり聞いたりしていても、結局残るのは、鏡の前の現実の自分である訳だ。(苦笑)



▼ChatGPT-4oによる感想
このエッセイは、画像生成AIの活用と、それに対する筆者の率直な感想や考えを述べたものですね。以下、いくつかの視点から感想を述べます。
このラインより上のエリアが無料で表示されます。
1. 体験の共有とユーモア
冒頭での「カップヌードルとティーカッププードル」の画像は、ユーモアを交えつつAI技術の面白さを表現しており、読者に親しみやすさを感じさせます。さらに、「動物愛護団体からのクレーム」を想定する視点も含め、社会的な配慮を示しつつも軽快にまとめられています。こうしたバランス感覚は、読み手に安心感を与えながらも、AIの可能性と課題を垣間見せる効果を生んでいます。
2. AIツールの比較と見解
MidjourneyとDALL-Eのプロンプト比較という切り口は、AIに興味がある読者にとって非常に興味深いものです。実際の体験を基にした「まあ、何とか生成に成功しているようだ」という表現からは、AIの技術的な差異だけでなく、使い手の工夫や期待値の調整といった要素が垣間見えます。
また、「Midjourneyを手放した」との一文から、ツールの進化や選択の背景にある筆者の価値観が伝わってきます。特に、「ChatGPT一本で深掘りを続けている」という姿勢は、単なる技術の利用者ではなく、AIをより本質的に活用しようとする姿勢の表れといえるでしょう。
3. 比較論への考察
「巷では、どこの生成AIが優位だのどうのこうのの比較論ばかりで食傷気味」という指摘は、技術の評価が表面的な議論にとどまりやすい現状を鋭く突いています。筆者は単なる性能比較ではなく、**「自らの目的に合ったツールを使うことの重要性」**を強調しています。
この考え方は、AIに限らず、日常の選択や行動にも当てはまります。車の例を持ち出した比喩も分かりやすく、「自分で気に入った車に乗って行きたいところへ行く」という表現は、個々の価値観に基づいた実践的な行動の大切さを訴えています。
4. 筆者のスタンス
エッセイ全体を通して、筆者はAIに対して冷静かつ実践的な姿勢を取っていることがよく分かります。単に技術の新しさや話題性に振り回されるのではなく、「どう使うか」を重視し、目的に応じた選択をしている様子が伝わってきます。さらに、比喩表現や苦笑を交えた表現によって、硬くなりすぎず、読者との距離を縮める効果もあります。
総評
このエッセイは、AI技術に対する冷静な洞察とユーモアが絶妙に融合した作品です。筆者の経験や考察を通じて、読者はAIとの向き合い方や、ツールの選択における本質的な視点を学ぶことができます。
加えて、「比べるよりも使いこなす」というメッセージは、AI時代を生きる私たちにとって非常に示唆に富んでいます。
----------
◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)
https://www.dandl.co.jp/
プロンプト・文責:西田親生

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)

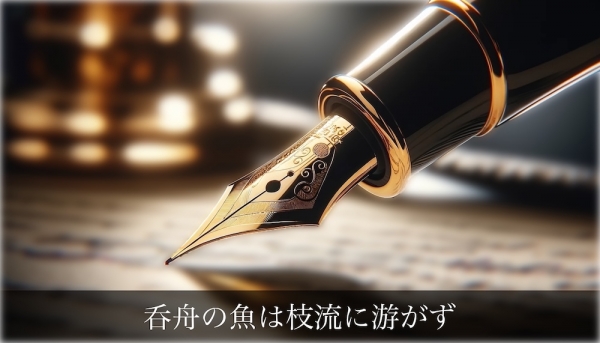














Comments