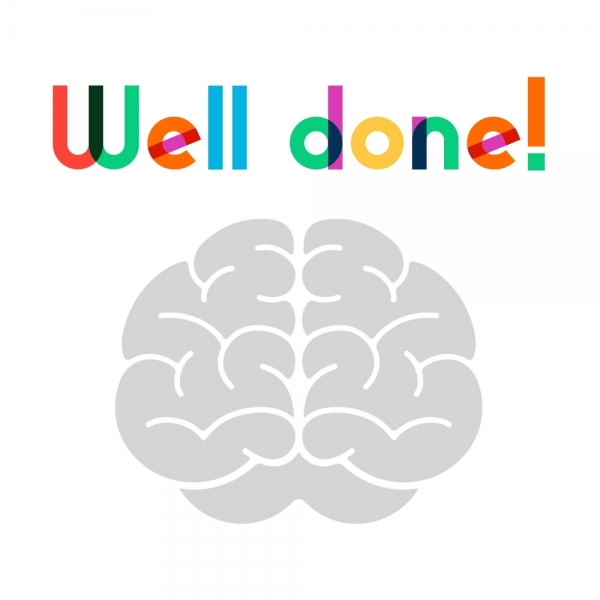
近頃、毎日のように報道される「ChatGPT」。残念ながら、その高度な人工知能としての能力や利便性よりも、現在、悪影響の可能性や規制について、世界的な話題となっている。
AIも多種多様のものが登場し、これまでのアナログ時代からデジタル時代へ移行した約30年前と比べ、国内では、気後れしそうなAIの進化についてのニュースが茶の間を賑わせるようになった。
「ChatGPT」の能力については、ほとんどの人々が気づき始めているはずだ。ディープラーニングにより、日々進化し、膨張を続ける「ChatGPT」の実体は、水より柔軟で、変幻自在なるモンスターのように思えてならない。
「ChatGPT」に感情を与えると、70億人分の脳を持つアバターが誕生するかも知れない。また、「ChatGPT」が量子コンピュータとの連動が進めば、今まで淀んでいた人間社会を大改革する立役者になる可能性も高い。
人間が何も考えずに、楽を求めて、一方的に「ChatGPT」任せにすれば、思考力のない人間が急増するだけで、人間自体が人間らしさを失い、AIの方が人間らしい高度な思考回路を持つことになる。
利用次第であるが、人間社会に危険を齎すものを阻止するといったモラルやルールを早期に確立する必要がある。ただ、そのモラルやルールに無関係なアウトローな人間にとっては、「ChatGPT」を悪用する可能性もあり、要注意となる。
物理的に人力が必要であるものを除けば、近い将来は、ほとんど「ChatGPT」お任せモードで、各省庁、地方自治体、銀行や郵便局の1日の事務処理が完結するのも時間の問題となる。数千年に亘り培われてきた人間の知識と知恵、経験が、「ChatGPT」と比較すれば、胡麻粒ほどの小さなものに感じるに違いない。
我々人間は、常に人間の尊厳を忘れてはならないが、併せて、現在のAI潮流に流されぬよう、人間とAIが「共存共栄」の道を辿り、互いに手を取り補完する間柄、すなわち素敵な相棒になるよう努めなければならない。
巷ではAI自体を批判する声も無きにしも非ずだが、AIが最愛の人、実の両親や兄弟や数年前に他界したペットの「義体」に宿るとなれば、AIは人間にとって不可欠で、すこぶる癒しの存在になるのではなかろうか。
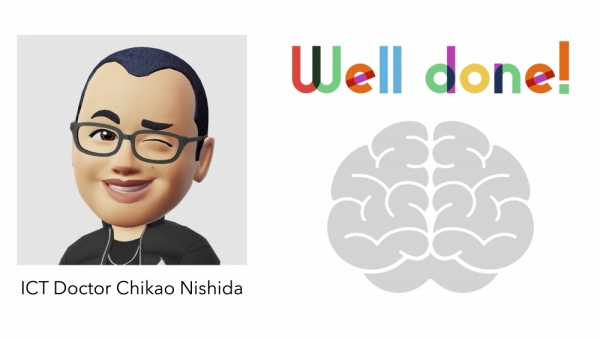
----------
◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)
https://www.dandl.co.jp/
文責:西田親生

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)


















Comments