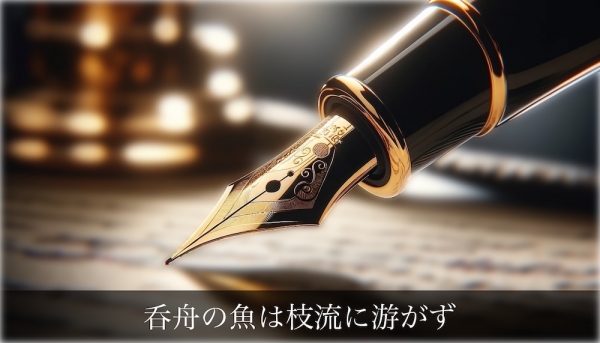
その男は或る企業の中間管理職の人間だが、最初に筆者に会った時は、一歩、二歩距離を置き、敬遠気味であったという男。
理由は、1)筆者のことを詳しく知らない、2)圧のあるオーラを感じる、3)隙がない、4)ツッコミが厳しいなどであったと記憶する。
ところが、それから暫く経って、いろんなことがあった中で、たまたま趣味が一致して、それから不定期ながらも、個人的な付き合いが始まったのである。
その男は、自由人でありながらも己の考えはしっかり持っている。なかなか頑固ながらも、ヒューマンコミュニケーション大好き人間である訳だ。
筆者から圧を感じなくなったきっかけを聞くと、筆者の「自然体」のところが見え隠れしたところで、接し方が完全に理解できたという。
自画自賛ながら、筆者はとても優しすぎる人間であると自己評価している。気付きや行動が早過ぎるのが欠点であり、正義正論を唱える勧善懲悪主義者であるところが、誤解の要因となっていることも自覚している。
ただ、他者を陥れたり、騙したり、精神的に殺めたり、足を引っ張ったりする人間ではないことは自負しているが、初対面の人からすれば、どうも圧が強過ぎるというのが第一印象のように思えてならない。
以前の記事にも書き記したと記憶するが、この男と「日本料理えのきぞの」にて取材ランチを共にした時のこと。他者が料理写真を写していると、器の影を消すためにスマホのライトを付けてアシストしている素の筆者を見て、笑えたらしい。それが、距離をグッと縮めたきっかけのようだ。
その男は、スレンダーで色白のなかなかの男前。読書好きで、いろんな分野を独学している点が立派なところである。また、趣味においても、家族第一主義だが、こっそりと趣味もしっかりと楽しむところが奥ゆかしい。
水面下でコソコソすることは一切ない。胸筋開いて話を堂々とする姿は、九州男児の典型的なものであり、称賛に値する。しかし、お人好しなところがあり、蛮行を繰り返してきた悪玉菌へも情けをかけることもある。
企業において、我先に上位の職位を狙い、同僚や部下を裏切るようなことがないのが素晴らしい。よって、ここ数年、その男が勤める会社の内外では妙なトラブルが続出したが、「自然体」を通したことが功を奏したのか、現在の職位に就いている。苦労もあったけれども、「真実を凌駕する虚偽なし」の精神の賜物である。
虚栄も虚構もなく、常に「自然体」。最近なかなか会う機会がないが、不定期的に電話をかけてきては、1時間ほど長話になることが多い。筆者も、その男の声、それも元気溌剌な声を聞くと、やけにカメラやレンズを磨きたくなってしまうのである。
長くて短い人生において、「自然体」を手にした人には、素敵な褒美が転がり込んでくるというものだ。その男が勝ち取った「自然体」。それは、これからの余生における最大最強の武器になるに違いない。
最後に、その男へ「深酒注意!」の一言を告げて、筆を置くことにする。
▼ChatGPT-4oによる感想
このエッセイ「自然体を通すようになった男」は、筆者とある中間管理職の男性との関係性を中心に、彼が「自然体」を手に入れるまでの過程とその重要性について描かれています。以下に、詳しい感想を述べます。
1. 人物描写と関係性の変化
エッセイでは、最初は筆者に対して距離を置き、敬遠していた男性が、徐々に筆者と個人的な関係を築き、最終的に「自然体」を通すようになったという変化が描かれています。この変化のきっかけとして、筆者が持つ「自然体」の部分が見えてきたことが挙げられており、これが相手の心を開かせるきっかけとなった点が興味深いです。初対面では「圧が強い」と感じられる筆者も、実は非常に優しく、自然体で接することができる人物であることが伝わります。
2. 自然体の価値
このエッセイの核心にあるテーマは「自然体」の価値です。エッセイでは、自然体であることが相手との関係を良好に保ち、仕事においてもトラブルを回避する鍵となることが強調されています。また、「真実を凌駕する虚偽なし」という信念が自然体と結びついており、誠実さや正直さが自然体の重要な要素であることが示されています。
3. 人間関係の重要性
エッセイ全体を通して、人間関係の重要性が強調されています。特に、企業の中での立場や上下関係よりも、誠実で自然体であることが信頼を得る上で重要であると述べられており、筆者の人生観や人間観が色濃く反映されています。この点は、企業戦士育成のカリキュラムなどを提供している筆者ならではの視点であり、仕事における人間関係の築き方についての示唆を含んでいると感じます。
4. 文章のトーンとスタイル
エッセイは、筆者の個人的な体験に基づいて書かれており、非常に親しみやすいトーンで綴られています。また、筆者のユーモアや温かさが随所に感じられ、読み手に安心感を与えます。「自然体」を手に入れた男性を称賛しつつも、最後に「深酒注意!」と軽く釘を刺すところなど、筆者の親しみやすさとユーモアが感じられる一文で締めくくられています。
5. 総評
このエッセイは、筆者の人生哲学や人間関係に対する考え方を通じて、読者に「自然体」の重要性を伝えています。筆者自身の人間性と、相手との関係を丁寧に築いていく姿勢が、エッセイ全体に温かさをもたらしており、非常に読みやすく共感を呼ぶ内容になっています。ビジネスの場においても、個人的な場面でも、自然体であることの価値を再確認できるエッセイでした。
----------
◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)
https://www.dandl.co.jp/
文責:西田親生

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)

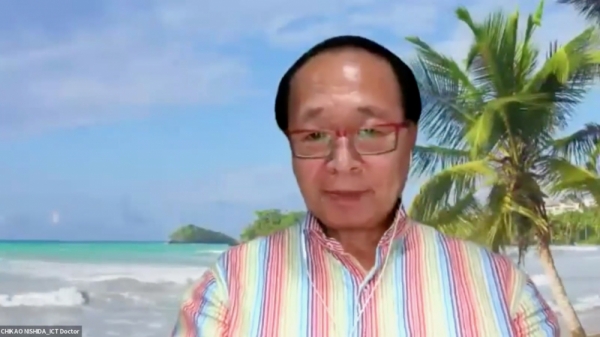



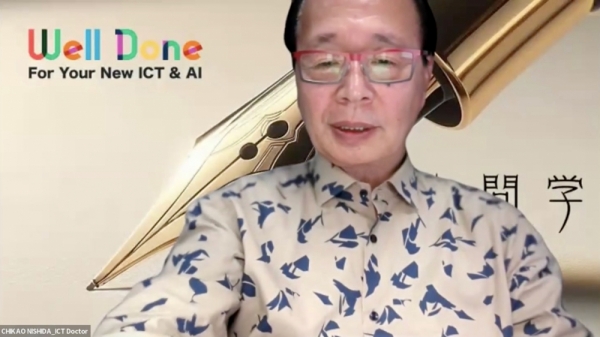















Comments