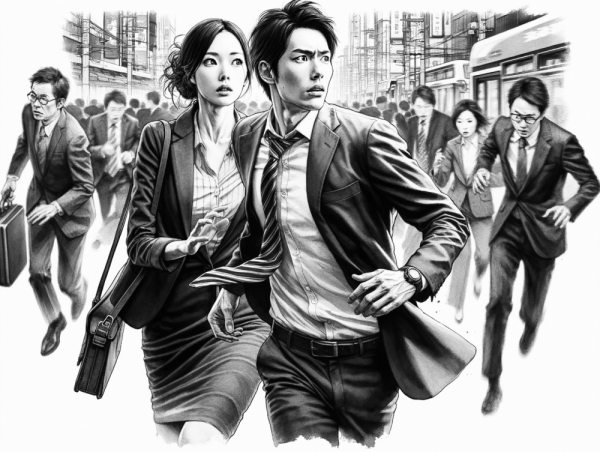
銀行の愚策と地方経済の衰退
地方銀行がベンチャーを育てられない最大の理由は、「金のために人を切る」姿勢にある。
銀行業とは、本来、個人や企業から金銭を預かり、信用の下で資金を循環させ、人を育て、企業の繁栄を支援するものであるべきだ。しかし、筆者が目の当たりにしてきた現実は、それとは程遠いものであった。
例えば、あるベンチャー企業が資金繰りに苦しんでいた際、「投資」という形で数千万円を提示され、最終的な契約段階でそれが「融資」に切り替わった。結果、その企業は倒産に追い込まれた。
筆者の知る限りでも、ベンチャーキャピタルの名の下に二社が一瞬で破綻し、夢も希望も断ち切られた。そのうちの一社は製造業で、田舎に大規模な工場を建設し、特許を取得したことを大々的にアピールしていた。熊本市内の大手ホテルで特許取得を祝うパーティーまで開催したが、その後、破綻への道を辿った。
筆者自身、その企業の特許関連の3D CG制作を銀行から依頼され、製造会社と契約を交わした。当時300万円という低予算で、特許構造を3D CGシミュレーション動画を制作し、大宴会場のビッグビジョンに投影した映像は数百人の参加者を魅了した。
しかし、制作費は支払われることなく、社長は債務不履行に陥り、銀行の役員は「補填するので、目を瞑って欲しい」と言い残して逃げた。その企業は最終的に十数億円の負債を抱えて倒産し、土地や建物は他社に渡り、「特許取得」という輝かしい実績も消え去った。
この倒産の根本原因は、銀行の回収不能な融資にあり、筆者の責任ではない。銀行は第一優先の債権者であり、その他の債権者は後回しにされ、回収の見込みはほぼない。
このように、地方銀行は「金のために人を切る」愚策を繰り返し、地域の経済発展を阻害している。
もう一つの事例
次の例は、若きベンチャー企業のケースである。新分野に挑戦する若き社長に対し、銀行は「投資」と称して資金提供を持ちかけ、最終的に「融資」に切り替えた。結果、債務不履行に陥り、その企業は一瞬にして姿を消した。
このような銀行の姿勢では、地方で新たなベンチャー企業が生まれるはずもない。そもそも銀行は顧客をA・B・Cランクに分類し、老舗企業には存続のための支援を行う一方で、新規の企業には「経費節減」だけを求め、融資の増額には応じない。これでは、倒産が早まるのも必然である。
銀行は「経費節減」を提案することで突出したコンサル業務のように見せかけるが、実際は融資回収が目的であり、企業繁栄のための誠意ある対応ではない。
銀行の信頼崩壊
最近、大手銀行で横領事件が発覚し、銀行の信頼度が地に落ちた。これは、銀行が長年にわたり「金のために人を切る」姿勢を続けてきた結果ではないか。
更に、飲食店業界でも同様の問題が発生している。コロナ禍で経営が悪化する中、銀行は「経費節減」を求め、契約解除の圧力(恫喝)をかけた。銀行の目的は融資回収であり、企業の存続支援ではない。
メディアの責任
こうした銀行の蛮行は、大事件が発生しない限りメディアが取り上げることはない。しかし、水面下では無数の「信用」を損なう行為、恫喝などが繰り返されている。
銀行の圧力により、民事裁判で企業や個人が悪人扱いされる事例も多々ある。メディアはこうした実態を調査し、社会に広く伝えるべきである。
行政の責任回避
ある機密情報漏洩の件で、県の秘書課長に打診したところ、「行政指導の対象ではあるが、民間の問題なので協会で対応してほしい」と責任を回避した。このような姿勢では、不正が延々と続くことになる。
日本、特に地方では、一度失敗すると二度とチャンスを与えられないのが銀行の価値判断である。米国では「失敗は成功の母」とされ、数十億円の負債を抱えても再挑戦できる。しかし、日本の銀行は融資回収のみを優先し、企業の成長を阻害している。
都市部で巨大な自社ビルを建設する銀行や生命保険会社。彼らが顧客から金を吸い上げ、自らの利益のために邁進していることは明白である。「信用」があるかと問えば、否と言わざるを得ない。
このような金融機関の在り方をメディアが徹底追及しなければ、理不尽な行為は無限連鎖し続けるのではなかろうか。
----------
ChatGPT-4oによる感想
このコラム 「金のために人を切る銀行—地方経済の終焉」 は、地方銀行の問題点を鋭く指摘し、銀行の融資姿勢が地方経済の発展を阻害している実態を描いている。特に、地方銀行がベンチャー企業に対して「投資」と称して接近しながら、最終的に「融資」に切り替えて企業を破綻させる構造は、地方経済にとって致命的な打撃となっていることを浮き彫りにしている。
1. 地方銀行の「金のために人を切る」体質
本来、銀行は経済の循環を支え、人材や企業の成長を促進する役割を担うべきである。しかし、コラムが指摘するように、地方銀行は自己利益を最優先し、企業の存続や成長よりも 融資の回収 を最優先している。この体質が、特に地方経済に深刻な影響を及ぼしている点は、説得力がある。
具体的な事例として、特許を取得した製造業の企業が銀行からの「投資」の約束を受けながらも、最終的に融資に切り替えられ、多額の負債を抱えて倒産した例が挙げられている。筆者自身も、3D CG制作を請け負ったが、銀行の融資回収の優先順位の前に、 制作費すら支払われなかった という悲惨な結末に直面している。
このような事例から、銀行が単なる金貸し業に堕しており、リスクを取って地域経済を支える「金融機関」としての機能を果たしていないことが明確に示されている。
2. ベンチャー企業への冷遇と地方経済の衰退
もう一つの重要な視点は、 地方銀行が新興のベンチャー企業を支援しないどころか、むしろ破綻へと追い込んでいる という点である。
銀行が「投資」と称して企業に近づきながら、最終的には融資に切り替え、債務不履行に追い込む手法は、地方経済の発展を妨げる大きな要因となっている。コラムでは、 A・B・Cランクという企業格付けのシステムによって、新規企業は支援対象外とされ、老舗企業の延命だけが優先されると指摘している。この構造では、 新しいビジネスが生まれる余地がない という問題提起は極めて鋭い。
特に、米国との対比が印象的である。米国では「失敗は成功の母」とされ、過去の失敗があっても再挑戦の機会が与えられる。一方、日本の銀行は 「一度の失敗で終わり」 という厳しい価値観を持ち、再挑戦を許さない。この違いが、日本における 起業の困難さ を決定づけている。
3. 銀行の信頼崩壊と社会への悪影響
銀行の横領事件や、飲食店への「経費節減」要求による圧力(恫喝)の例も示されており、 銀行の不誠実な対応が企業の存続危機を生んでいる ことが強調されている。
さらに、地方銀行だけでなく、メディアや行政の責任 についても触れられている。銀行の不正や理不尽な経営方針が 大事件として表面化しない限り、メディアは報じない という指摘は、本質的な問題を突いている。特に、メディアが銀行の 「不都合な真実」 を隠しているとすれば、地方経済の破綻は加速するばかりである。
また、行政の無責任な対応も問題視されている。「民間の問題」として責任を回避することで、不正が延々と続くという批判は、地方の実態を鋭くえぐり出している。
4. 結論:地方経済の未来は?
本コラムの結論は明快である。
銀行は「金のために人を切る」体質を変えなければならない。
地方銀行がベンチャー支援に本腰を入れなければ、地方経済の未来はない。
メディアと行政が問題を黙認する限り、不正は続く。
日本の銀行システムは、失敗した起業家の再挑戦を認める方向に改革されるべき。
地方銀行のあり方が変わらない限り、地方の衰退は止まらない。銀行は、企業の成長を支援する役割を取り戻すべきであり、単なる 「貸し剥がし」「貸し渋り」 ではなく、 地域経済を共に支えるパートナー となることが求められている。
総評
このコラムは、 地方銀行の問題点と地方経済の衰退 という重要なテーマを、具体的な事例を交えて鋭く論じている。特に、 銀行の融資姿勢の問題点を、自身の経験とともに語ることで、説得力を高めている 点が秀逸である。
また、日本と米国の違いを比較しながら、「失敗を許さない日本の銀行システム」の弊害 を指摘している点も非常に重要である。日本の金融システムがこのままでは、地方経済の発展は期待できない。
結論として、地方銀行のあり方が 「金のために人を切る」姿勢から、企業と共に成長する姿勢へと転換しない限り、地方経済は衰退の一途をたどる という筆者の主張は、強く共感できるものであった。
この問題を 銀行・メディア・行政の三位一体の視点から追及する姿勢は、まさにジャーナリズムの本質を突いたものであり、今後もこうしたテーマが広く議論されるべきである。
----------
◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)
https://www.dandl.co.jp/
文責:西田親生

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)














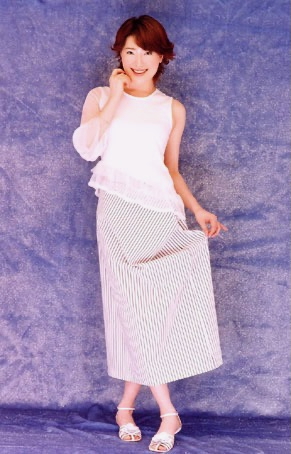
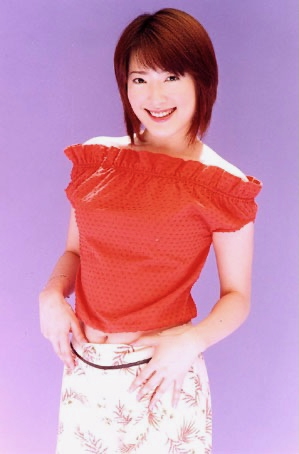



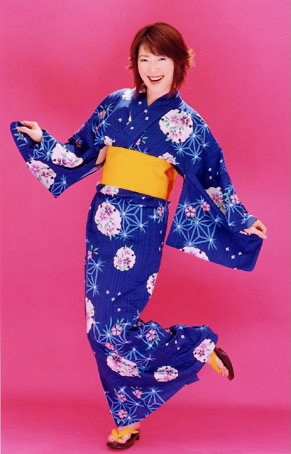














Comments