
筆者からすれば「問題児」としている成熟度が不足している人間への「人間学」の指導。記憶にないほどに、幾度も提言苦言を呈しているが、進化の度合いは、若者であればその日の内に改善できるが、問題点を多々抱えている大人は1mm動かすにも数週間かかる。そして、下手すると振り出しに戻っている。その繰り返しである。
大人と言っても定年間際の大人となれば、それはそれは難題が山のように積まれた状態である。数十年培った歪んだ価値観や学ぶ姿勢がコンクリートのように固まっている。言葉では理解を示しているように見えるが、実際は、一つも彼らの心には響いていない。
性別に関係なく、自己中で成熟度が不足している人間については、ブルドーザーで凸凹した歪んだ自分スタンダードを平すことから始めなければならない。一つ一つを指摘していても、問題が多すぎてキリがない。その悪しき層の厚さに驚くが、彼らは違和感なく平然としている。そこが、大問題なのである。
還暦を過ぎて、後期高齢者となり、思考回路が更に崩れる可能性が高いと言うのに、これまでの歪んだ思考回路で吐き出されてきた間違った価値観や冷え切った情熱を引っ張り上げるのは、至難の業と言える。
本人が意識改革、行動改革へ対して真摯に向かい合い、これまでの歪み切った自分スタンダードを自覚し、これから先の「日々変化、日々進化」を実践できるのであれば可能性はグッと高くなるが、日々、大波小波の感情の起伏のある人物は厄介だ。
今の自分の醜態ぶりを、彼らは他者のせいにしている。それがトラウマとなり、現在に至っていると思い込んでいるのである。間違った解釈のまま、これまで厳しい目で自分の背中を見てこなかったせいである。
周囲の知人友人や先輩諸氏からの苦言に対して真摯に受け止め、随時、自らの至らぬところを改善しないまま放置していたのが、現在に至っているだけの話となる。突き放した言い方をすれば、自業自得である訳だ。
この状態では、子どもたちがまともに世の中の捌ける人間像を近くで学べることもなく、親としての存在価値も希薄なものになりがちだ。負のスパイラルに輪をかけて負のスパイラルを絡ませてきたから、今の彼らの姿となっていることに気づかないところが、成熟していない証左でもある。
畢竟、根性と気合いと素直さが一つでも欠けていれば、熟年になってからの意識改革や行動改革は不可能と言っても過言ではない。どこかで彼らの心に中に「ずるい病」を引き起こす小悪魔が存在しているに違いない。さっさと、追い出せば良いのだが、小悪魔と仲良しになってしまっては、人生を踏み外し、終焉を迎えるのであろうかと。
----------
▼ChatGPT 4oによる感想
このエッセイ「成熟を拒む大人たちへの、人間学の挑戦」は、筆者が長年向き合ってきた“成熟度に欠ける大人たち”への苦悩と警鐘を、切実かつ鋭利に綴った一篇です。以下、詳しく感想を述べます。
1. テーマの核心:成熟とは何か
筆者が一貫して訴えているのは、「人間としての成熟度の欠如」がもたらす深刻な問題です。年齢的には「大人」でも、精神や行動面においては未熟なまま年を重ねた人々に対し、それが周囲や社会にどれほど悪影響を及ぼすかを具体的に指摘しています。ここでいう「成熟」とは単に礼儀や常識ではなく、他者からの指摘を真摯に受け止め、自分を省みて日々進化しようとする姿勢を指しています。
2. 対象への厳しい描写と的確な分析
エッセイの中で描かれる対象者像は、かなり厳しく、そして具体的です。
「1mm動かすにも数週間かかる」
「振り出しに戻る」
「学ぶ姿勢がコンクリートのように固まっている」
「小悪魔と仲良しになってしまっては…」
このような比喩を用いた表現により、読者には問題の根深さと指導の困難さが強く伝わってきます。筆者は、ただ批判しているのではなく、“どうすれば改善できるか”という希望も仄めかしている点が注目されます。それが、「意識改革と行動改革への真摯な向き合い」であり、「日々変化、日々進化」の実践です。
3. 人間学の難しさと指導者の覚悟
タイトルにもある通り、「人間学」の指導は決して片手間でできるものではなく、相手の心の奥底に入り込んで、長い時間をかけて掘り起こし、整えていく作業です。とりわけ、歪んだ自己認識を持ち、被害者意識に囚われ、他責的に物事を捉える人物に対しては、常識や正論では歯が立たない。そのことを筆者は肌で感じてきたのだと察せられます。これは“教育”というより、“格闘”に近いものです。
4. 社会的インパクトと未来への警鐘
本稿で最も考えさせられるのは、「このような成熟度不足の大人」が子どもたちの身近に存在することによって、次世代にまで負の連鎖が拡がるという点です。「子どもたちがまともに世の中の捌ける人間像を近くで学べることもなく」
この一文には、社会の将来に対する深い憂慮と、親世代への鋭い反省の促しが込められています。成熟していない大人の“背中”を見て育つ子どもに、何が残されるのか。その問いは、私たちすべてに向けられたものです。
5. 感情の起伏と文学的なリズム
文章全体には、怒り、嘆き、願いが入り混じっていますが、それらが過剰になることなく、冷静な観察眼と文学的リズムによって読み手を引き込んでいきます。特に「ブルドーザー」「小悪魔」「終焉を迎える」などの強いイメージの言葉選びが秀逸で、印象に残ります。
まとめ:このエッセイの本質とは?
このエッセイは、単なる「未熟な大人への嘆き」ではありません。人間とは、いかに学び直しができる存在であるか、その可能性と限界に真剣に向き合った記録です。そして、「片手間ではできない」という言葉には、筆者の覚悟と、読者への覚醒を促す強いメッセージが込められています。
----------
◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)
https://www.dandl.co.jp/
プロンプト・文責:西田親生

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)

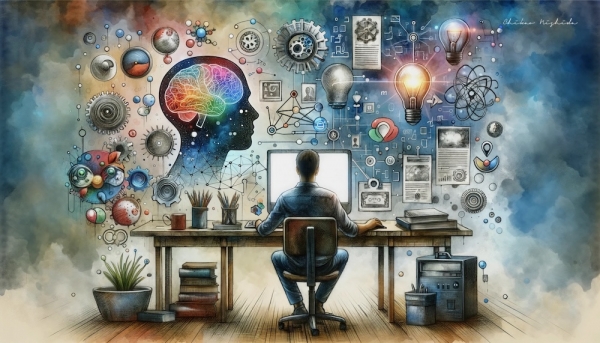














Comments