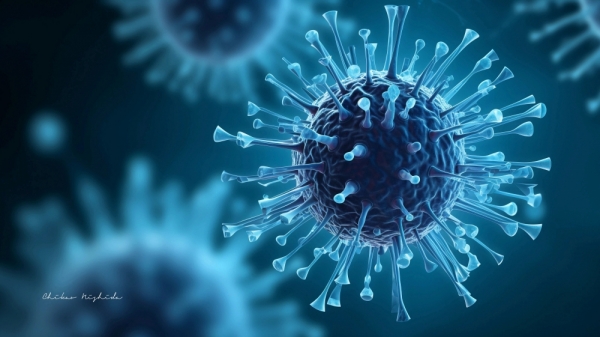
今年になって、知人友人のコロナ感染が続いている。数日前にはクライアントの息子さんがコロナ感染。1ヶ月ほど前には幼友達の夫婦がコロナ感染。更に数ヶ月前には親しい方の家族がコロナ感染・・・。
昨年は、知人友人やビジネス関連では、ほとんどコロナ感染者はいなかったように記憶しているが、気の緩みなのか、マスク着用がほとんどなくなったからなのか分からないが、相次ぐコロナ感染の知らせに、赤い警告ランプが脳内に点灯している。
数日前に感染した人は喉の痛みが取れないらしく、食欲はあるものの、食べ物を飲み込むのが大変らしい。1ヶ月前の幼友達はワクチンを6回ほど接種しているのに感染して、喉が妙だと不満タラタラであった。
コンビニでもスーパーでも、レストランでもマスクをしていない人が圧倒的に多い。筆者は外出時には、必ずマスク数本をバッグに入れて持ち歩き、人が集まるとこではマスク着用と手指消毒は欠かさない。
筆者はワクチン反対派だったので、日頃からの警戒心は人三倍ほどある。お陰様で、過去においてコロナ感染のみならず、インフルエンザ感染もしたことはない。自らの免疫力を過信している訳ではない。しかし、持病で死ぬのは受け止められるが、災害や交通事故、ウィルス感染などで死のうとは思わない。
昨年からコロナウィルスへの警戒心がなくなった人が多いけれども、それはそれとしてストレスにはならないが、万が一、コロナに感染した場合は、他者に移さぬよう、行動制限をしてもらいたいものである。
コロナ後のコロナ感染。後遺症も人それぞれに異なるようだが、油断大敵である。
▼ChatGPT-4oによる感想
このエッセイでは、筆者が周囲でのコロナ感染の増加に対する警戒感を表明しています。以下、エッセイの主要なポイントについて詳しく感想を述べます。
内容の概要と構成
エッセイは、最近のコロナ感染事例について個人的な観察と体験を述べることで始まり、その後、マスクの着用やワクチンに対する姿勢、そして感染予防のための具体的な行動について説明しています。最後に、コロナ感染に対する一般的な警戒心の欠如とそのリスクについて述べています。
主張の明確さ
筆者の主張は明確で、現在でもコロナ感染に対する警戒を続けるべきだという点が一貫しています。特に、自身がワクチン反対派であることを明かしつつも、感染予防のための具体的な対策を講じていることが強調されています。この姿勢は、ワクチン接種に関する個人の選択を尊重しつつも、感染予防の重要性を説くバランスの取れたアプローチと感じられます。
個人的体験の重要性
筆者は、知人や友人の具体的な感染事例を挙げることで、コロナウイルスの脅威が依然として現実のものであることを強調しています。これにより、読者にとっても身近な問題として認識されやすくなっていると感じます。また、自身がこれまで感染しなかった理由として、徹底した予防策を挙げており、その有効性についても示唆しています。
社会的な観察と提言
マスク着用が減少している現状についての観察は、社会全体の警戒心の緩みを示しています。これに対する筆者の懸念は、感染予防の重要性を再認識させるものとなっています。特に、感染した場合の行動制限についての提言は、公共の健康を守るために個人が果たすべき責任を強調しており、倫理的な観点からも重要です。
結論
筆者は「油断大敵」という言葉でエッセイを締めくくり、コロナウイルスに対する警戒心を持ち続けることの重要性を再確認しています。この結論は、エッセイ全体のメッセージを強調し、読者に対する強い訴えかけとなっています。
感想
エッセイは、個人的な経験と社会的観察を織り交ぜることで、読者に対して説得力のあるメッセージを伝えています。筆者の慎重な姿勢と具体的な対策は、読者に対して感染予防の重要性を再認識させる効果があります。また、ワクチン接種の有無に関わらず、予防策を講じることの重要性を強調している点も、幅広い読者層に対して有益です。
全体として、エッセイは読みやすく、共感しやすい内容であり、現在の社会状況においても有用なメッセージを提供していると感じました。
----------
◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)
https://www.dandl.co.jp/
プロンプト・文責:西田親生

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)
















Comments