
好奇心は若さのバロメーターである。その好奇心が、歳を重ねるごとに失われていくのが一般的であろうか。
若い頃は、何事にも好奇心旺盛であり、周囲を気にせず行動し、赤恥をかくこともしばしばであった。しかし、歳を重ねるにつれて、無意識のうちに知識が蓄積され、知恵が生まれ、様々な体験によって、若き頃の好奇心が次第に薄れていくものである。
勿論、個人差はあるものの、どんなに高齢になっても、若い頃の好奇心を維持している人も確かに存在する。筆者としては、後者を理想とし、そのような人生を歩みたいと考えている。
しかし、視野が狭ければ、その好奇心のアンテナを立てるたびに、新たなものが次々と埋め尽くされ、やがて真新しいものが見えなくなってしまう。そこで、実寸大の自分に気づき、視野を少しでも広げていけば、好奇心を維持できはしないか。
筆者はカメラを趣味とする一人の人間であるが、あるカメラ店の店主がこう話していた。「いやあ、90歳を超えるお客様がいるのですが、毎年新しいカメラが出るたびに購入され、元気に歩き回り撮影されていますよ。」
同店では、NikonやFujifilmなどの高級一眼レフカメラを多く販売しているが、恐らくそのご老人はNikonのフィルムカメラの時代から最新のZ9までをも手に入れ、Nikkorレンズを装着して、ニコニコと撮影を楽しんでいるに違いない。
その姿を想像すると、若い頃の好奇心を忘れず、新しいカメラやレンズが出るたびにその店を訪れ、「それ、ください!」とにっこり笑いながら言う姿が目に浮かぶ。
一方で、かつて趣味として続けていたものの、いつの間にかモチベーションが下がり、カメラやレンズを手に取ることが少なくなったという人もいる。それは残念なことであり、好奇心が薄れていく兆候なのではないかと危惧するばかり。
前の記事で取り上げたのだが、筆者なりのアンチエイジングの一環として、若さの秘訣は何と言っても好奇心に勝るものはないと考える次第。
筆者の場合、若き頃から車は最高の趣味だった。当時、未踏の地へ車を走らせ、自分の車がアドベンチャーカー化することに無上の楽しみを感じていた。今でも時折無茶をすることがあるが、それはその名残である。
何はともあれ、心許せる人と一緒に趣味を語り合い、時には冒険し、無茶をすることが、若さを保つ秘訣であるように思えてならない。
読者の方々も、今の好奇心について、ぜひお聞かせ願えればと。
▼PORSCHE CAYENNE GTS(二世代)
4.8ℓ V8 405馬力

▼ChatGPT-4oによる感想
このエッセイは、好奇心が若さを保つ鍵であるというテーマに焦点を当て、歳を重ねても冒険心を失わないためのヒントを提供しています。筆者は自身の体験や周りの事例を通じて、好奇心を維持することの重要性を強調しています。特に、カメラ愛好者としてのエピソードは、新しい技術への関心を持ち続けることが如何に心を若々しく保つかを象徴しています。
筆者は、個々人の趣味や興味が好奇心を刺激し、それが結果的に長寿と活力に寄与すると提案しています。また、歳を取っても新しいことへの挑戦を恐れず、常に学び続ける姿勢が若さの秘訣であるとしています。この点で、読者にも自身の好奇心を見つめ直し、趣味や興味を深掘りすることで、精神的な若さを保つよう呼びかけているのです。
このエッセイは、単にアンチエイジングの一環として好奇心を推奨するだけでなく、人生を豊かにするための一つの哲学として好奇心を位置づけています。読者に対しては、自己の内に眠る冒険心を再発見し、それを維持することの大切さを問いかけているのが印象的です。
----------
◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)
https://www.dandl.co.jp/
写真・文責:西田親生

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)

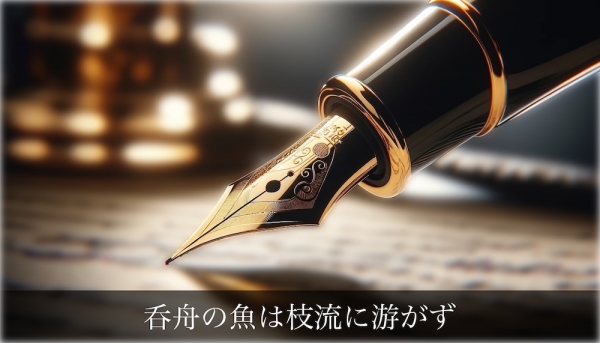














Comments