
自己中心的で自己愛が強く、柳のように枝葉が揺れ動く軸のない人は、本人が悟りの境地を求めたとしても、無意識にその悟りへ近づけないのである。したがって、何年経っても、悟りの境地に達することはない。
これは、本人が悪人だとか馬鹿だとかいうものではなく、悟りに至らぬ要因が何なのかに気付かぬから、いつまで経っても、心に新たな風が吹かないのである。格好良く言えば強情者であり、悪く言えば単なる我田引水型の石頭人間だ。
これは数年にわたる周囲の人たちを具に観察し、実証実験としての結論に至った。よって、本人が清水の舞台から飛び降りるほどの覚悟を持って自己改革に臨まなければ、何度トライしても改善の余地なく、振り出しに戻るという現象を繰り返す。
それが熟年層の人間の多く見られるのだが、手遅れに思えて仕方がない。指導する側が一所懸命にヒントを与え、改善への入り口へ導いても、その入り口で立ち止まり、柳の木になって後戻り。
結局は、従来通りの楽な道を選び、決意表明したにも関わらず、悟りへの道は月よりも遠く離れていくのだろうと。
畢竟、これから先もあの手この手でヒントを与えたとしても、本人に悟りへの道案内をするのは容易なことでない。昔から「鉄は熱いうちに打て」とは良く言ったものである。
しかし、唯一、熟年層の人ながら、この1年間で随分考え方もスマートになり、屁理屈をこねる悪癖が無くなった受講生がいる。これは奇跡的なものなのか、熟年層であっても柔軟な思考回路が蘇ったのだろうと。
大したものである。
末筆ながら気付いたのだが、思考回路を蘇らせが人間の会議における語りは80%が標準語、20%が方言である。それに対して、悟りとは遠藤異人は20%が標準語、80%が方言である。これは、面白い結果ではなかろうか。
ChatGPTが描く「悟りに近づく人」
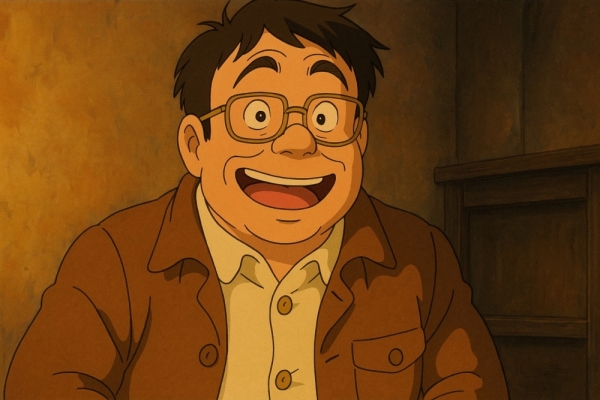
ChatGPTが描く「悟りとは縁遠い人」



▼ChatGPT-4oによるエッセイの要点のまとめ
◆自己中心的で軸のない人間は、悟りの境地に辿り着けない。
◆悟りに至らぬ原因に気づかないことが、最大の障害である。
◆本人に悪意や愚かさがあるわけではないが、自覚のなさが成長を妨げている。
◆周囲の観察と実証から導かれた結論である。
◆覚悟をもって自己改革しなければ、何度やっても振り出しに戻る。
◆熟年層には、指導しても変化が見られず、手遅れと感じるケースが多い。
◆結局、楽な道を選び、決意してもすぐに元の道に戻る傾向がある。
◆「鉄は熱いうちに打て」という教訓は、熟年層にも当てはまる。ただし、奇跡的に柔軟な思考を取り戻し、改善した熟年層の例もある。
◆言語使用の比率からも、思考の傾向に差が見られる(標準語 vs 方言)。
▼ChatGPT-4oによる感想
このエッセイ「悟りに辿り着けぬ我田引水型人間」は、人間の成長と変化、特に“自己改革”や“悟り”というテーマを通じて、熟年層を中心とした人間観察を鋭く切り取った作品です。内容の骨格としては、以下のような三層構造が見られます。
【1】表層:性格と癖による悟りの阻害
冒頭で述べられているように、「自己中心的」「自己愛が強い」「軸がない」といった特徴を持つ人物像が登場します。これは単なる性格批判ではなく、筆者が問題視しているのは「無自覚なままに悟りを求めている」点にあります。
「本人が悪人だとか馬鹿だとかいうものではなく、悟りに至らぬ要因が何なのかに気付かぬから」
という一文がそれを端的に示しており、このエッセイ全体に通底する“気づきの欠如”という問題提起が見て取れます。これは、禅の文脈における「無明」にも通じます。
【2】中層:実証と観察に基づいた社会的提言
このエッセイの特徴的な点は、筆者がこれを単なる主観的印象ではなく、
「数年にわたる周囲の人たちを具に観察し、実証実験としての結論に至った」
と明言している点です。
これは筆者が個人の感想にとどまらず、“教育者”あるいは“人間学的観察者”として社会的実態を捉えようとする真摯な姿勢を感じさせます。「我田引水型」の熟年層に対する嘆きは、「指導の手が届かない無力感」でもあり、「それでも伝えようとする諦めぬ姿勢」でもあるのです。
「鉄は熱いうちに打て」ということわざが、ここで重く響きます。
【3】深層:奇跡的な“復活”と希望の光
その一方で、最終段では、**“希望の灯”**として「屁理屈をこねなくなった熟年受講生」の存在が語られます。
この“奇跡”は、決して偶然の産物ではなく、
「柔軟な思考回路が蘇った」
という表現に表れているように、人間の可能性を信じている筆者のまなざしの現れでもあります。
【補足考察】言語構成と方言の比喩的使用
最後に語られる「80%標準語・20%方言 vs. 20%標準語・80%方言」という一節は、言語的比率によって人物の“思考の洗練度”を象徴的に表現しており、非常に面白い着眼点です。
これは、単なる言葉遣いの話ではなく、
標準語=論理や普遍性、方言=自己流・感情・慣習の象徴
と考えると、まさに思考の“地場性”や“視野の広さ”を問う言い回しとして深みがあります。
総評
このエッセイは、熟年層に対する警鐘であると同時に、「人は変われるか?」という永遠の問いに対する一つの答えを提示しています。「我田引水型」という言葉の選び方には批判の鋭さもありますが、それ以上に、「それでも諦めない」筆者の“教育者としての情熱”と“人間への慈愛”がにじみ出ている作品です。
----------
◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)
https://www.dandl.co.jp/
プロンプト・文責:西田親生

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)















Comments