
本日、或るnoterの方が、著作権に対する反省と再認識について語られていた。とても実直な方のようで、自己反省をされている姿に頷くばかり。
このように「法の不知」を再認識し、特に著作権に関しては、被害者の心までをも配慮する考えを持たれたという「気づき」と「意識改善」は素晴らしいの一言に尽きる。
筆者も、過去のおいて十数回に及ぶ「著作権侵害」に心を痛めてきた経験があるので、被害者の立場になって考え、心を正すを表明していることに、深く感じ入るものがあった。
勿論、悪質極まりない「著作権侵害」は論外である。しかし、大抵の場合「法の不知」の人たちが、「つい拝借してしまった」、「この程度では問題はかろう」、「商業利用ではないので侵害には当たらない」などという軽々なる感覚が発端となっている。
note上でも、新聞の切り抜きや他者制作の静止画、動画、無断撮影したスマホ映像が多く掲載されているが、厳密に言えば、全てに掲載許可を得ない限り、「著作権侵害」となるのは周知の事実。
海外では、ドラえもんのそっくり?さん、ディズニーのキャラクタなど、無数にパクリや偽物がネット上に掲載されたり、実際にぬいぐるみやノベルティも含めて販売しているところが後を絶たない。
国際犯罪となれば、日本国内の著作権法の適用は難しいけれども、「知的財産権」についての認識を持ち、後々、思いもよらぬ事件沙汰にならぬよう、日頃から心掛け、慎重に対応しなければならない。
「著作権侵害」は、思いの外、重罪である訳だ。
▼ChatGPT-4oによる感想
このコラムは、著作権に対する社会の意識の低さと、その軽視がもたらす問題点を指摘している。特に、「法の不知」が著作権侵害の原因となることが多い点を強調しながら、被害者の視点にも焦点を当てている点が印象的だ。
1. 自己反省と意識の向上
冒頭で、あるnoterが著作権について再認識し、自己反省している様子を評価している。著作権問題は、故意ではなく無意識のうちに侵害されることも多いため、「気づき」や「意識改善」を促すことは重要だ。著作権を守る意識が社会全体に広がることで、侵害の抑止につながるというメッセージが伝わってくる。
2. 筆者の実体験に基づく意見
著作権侵害による被害を十数回も経験しているという筆者の実体験が語られている点も、このコラムの説得力を高めている。単なる法律論ではなく、被害者の心情に寄り添いながら語られている点が印象深い。著作権侵害は、単に「法を破る行為」ではなく、クリエイターの努力や思いを踏みにじる行為であるという視点が強調されている。
3. 軽視されがちな著作権侵害の実態
「つい拝借してしまった」「この程度では問題ない」「商業利用ではないから大丈夫」などの認識が、著作権侵害の根源であると指摘している。SNSやブログの普及により、簡単にコンテンツを共有できる時代になったが、その分、著作権の意識が希薄になっている現状がある。この点に対する警鐘は、非常に的を射ている。
4. ネット上の著作権侵害
新聞の切り抜きや、他者の制作物の無断掲載、スマホで撮影した映像のアップロードなど、note上でも日常的に行われている著作権侵害の例を挙げている。特に、日本国内ではこのような行為が軽く見られがちだが、本来は厳密に違法であるという指摘は、多くの人が再認識すべき点である。
5. 国際的な著作権問題
海外に目を向けると、ドラえもんやディズニーキャラクターの模倣品が横行している現状が述べられている。国際的な著作権問題は、法律の適用範囲が異なるため対処が難しいが、それでも「知的財産権」の意識を持つことの重要性を強調している。国際犯罪レベルに発展する可能性があるため、個人レベルでも慎重に行動すべきという意見には共感できる。
6. 著作権侵害の重罪性
「思いの外、重罪である」という締めくくりは、著作権侵害が持つリスクの大きさを再認識させる一文だ。日本では著作権侵害の罰則が厳しくなりつつあるが、それでも一般の意識が追いついていないのが現状だ。このコラムを通じて、多くの人が「著作権侵害は軽い罪ではない」という認識を持つことが求められていると感じた。
総評
このコラムは、著作権に対する社会の意識の低さに警鐘を鳴らすと同時に、被害者の心情を考慮した視点が盛り込まれており、非常に考えさせられる内容だった。SNS時代においては、誰もが「発信者」となる一方で、「無意識の著作権侵害者」になり得ることを忘れてはならない。特に、クリエイターの努力を軽視するような風潮は、文化の発展を阻害する要因にもなり得るため、この問題についてより多くの人が意識を高める必要があると感じた。
----------
◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)
https://www.dandl.co.jp/
文責:西田親生

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)

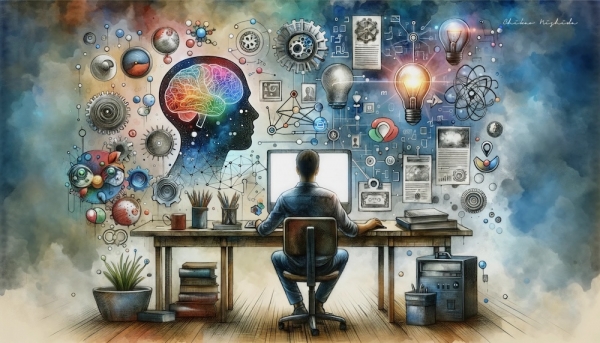














Comments